山野の生活通信
皆様の健やかな毎日にお役に立てるよう、季節にあわせた情報をピックアップしてみました。
Vol.94 季節の変わり目に起こる体調不良に要注意!
2024年9月この時期、疲れが取れない、身体がだるいなどの症状がありませんか。季節の変わり目に起こる体調不良の予防方法をご紹介します。
体調不良の症状と原因とは
体調不良の症状はさまざま
厳しい夏の暑さも、少しずつ収まる季節の変わり目。原因が分からない身体の不調が続いていませんか。
◆寝つきが悪く、寝ても疲れが抜けない
◆頭痛・めまい・立ちくらみがおきる
◆食欲がわかない・胃腸がもたれる
◆一日中気分が重い・気分が晴れない
◆イライラやストレスを感じやすい
これらがよくある季節の変わり目からくる、体調不良の症状です。
夏の疲れからくる自律神経の乱れ
次のようなことで自律神経が乱れ、体調不良につながります。
◆一日の寒暖差 朝晩の涼しさと日中の暑さによる急激な温度差
◆季節の変化 秋にかけ日照時間が短くなり、外出する機会も減ることでの日光不足
◆夏の疲労の蓄積 夏にとった冷たいもので、胃腸の機能が低下体調管理と生活習慣で予防
自律神経のバランスを整える
◆温度変化に備える 屋外と屋内の気温差が大きいと体への負荷がかかります。温度差は5~6度以内が理想的です。下半身は冷えやすいので、ひざ掛けなどを活用しましょう。
◆十分な睡眠をとる 規則正しい睡眠サイクルを維持することで、体調や免疫力の維持に役立ちます。寝る前のリラックスタイムや、寝室の環境整備も忘れずに。
食事や運動でリフレッシュ
◆バランスのとれた食事で予防する 野菜、果物、穀物、たんぱく質、脂質をバランスよくとることが重要です。収穫の秋でもあり、ミネラルやビタミン豊富な野菜や果物を積極的に摂取しましょう。
◆自然を楽しむ ハイキングやウォーキングで自然を満喫し、気分をリフレッシュしましょう。Vol.93 上手な夏野菜の選び方と保存方法!
2024年7月1年中、出ている野菜がありますが、味や栄養分は旬のものがいちばん!
旬の夏野菜の上手な選び方と保存方法をマスターして、健康づくりに役立てましょう。代表的な夏野菜の選び方

トマト
持ったときに重く、色が全体的に赤く、丸くて形の良いものがおすすめ。ヘタの色が黒ずんでいるのは古いものなので注意しましょう。
きゅうり
手で触れたときにいぼがチクチクしていて、両端のヘタの切り口がみずみずしいものを。
ナス
皮に光沢があり色が鮮やかなものを。皮が茶色くなっていたり、傷があるものは避けましょう。ヘタにあるトゲが鋭いものほど新鮮で、アクも少なくおいしく食べられます。
カボチャ
持ったときにズッシリ重く感じるものを選びましょう。丸ごとの場合は、冷暗所で長期保存できます。カットして売られているものは、実の色が濃くわたの部分がしっとりしていて種がぎっしり詰まっているものを。余りはわたと種を除いてラップに包んで保存します。
野菜を長持ちさせるには
乾燥させて冷蔵保存
トマト,きゅうり,ナス,カボチャなどは、水分を与えないで冷蔵庫で保存。特に、きゅうりは水気を嫌います。
冷蔵庫に入れず冷暗所に
丸ごとのカボチャ、さつま芋やしょうがなどは冷蔵庫に入れないようにしましょう。低温障害をおこして味が落ちてしまいます。

立てて冷蔵保存
葉野菜は乾燥が苦手。しめらせた新聞紙やペーパータオルで包みビニール袋に入れて冷蔵庫で保存しましょう。
横に寝かせると上に成長しようとして栄養分を使い果たし腐りやすくなるので、立てて保存するほうが長持ちします。アスパラやスィートコーンなどもこの保存方法で。Vol.92 調味料だけじゃない、日常生活での塩活用法!
2024年5月塩は味付けするだけでなく、これからのジメジメ季節にも活用法があります。塩の特性を生かし、日常生活で活用できる方法をご紹介します。
身体の役割に欠かせない塩

身体の中での塩の働き
◆体内細胞のバランスを保つ 体内の細胞の働きを保つために、細胞の内と外の水分濃度バランスを一定に保っています。
◆吸収・消化を助ける 胃の中で食べ物を殺菌し、消化を助けてくれます。腸内ではブドウ糖やアミノ酸など栄養素の吸収や分解を促します。
◆脳や身体に情報を伝達する 物を触った感覚や手足の筋肉を動かすなど、脳からの命令を伝達する役目があります。適度な塩分摂取を
塩を摂取しすぎると高血圧や腎臓、心臓の病気を引き起こすといわれ注意が必要です。
しかし、塩分が不足してしまうと、これからの時期は熱中症を引き起こしてしまいます。汗で失った塩分と水分はしっかり補給しましょう。味付けだけでない塩の活用法
洗剤として活用
茶渋や汚れを取り除くための自然洗剤としても機能します。スポンジに塩を付けて擦れば汚れが落ちやすくなります。
病気予防として活用
塩水うがいで喉の傷みがやわらいだり、喉の菌やウイルスを洗い流してくれたりする効果があります。
香りづけとして活用

味付けの基本となる塩。ローズマリーやバジルなどのハーブ、ガーリックパウダーやブラックペッパーなどのスパイスを混ぜれば、新しい味が楽しめます。
飲料として活用
これからの季節に気をつけたい熱中症。スポーツドリンクや塩レモン水などで予防しましょう。塩分補給することで、身体のバランスを整えることができます。ただし、飲み過ぎには注意が必要です。
Vol.91 ランチに行楽においしいお弁当作りのコツ!
2024年3月草木が芽吹き、だんだんと暖かくなる季節。お弁当を持って出かけませんか。毎日のお弁当や行楽弁当作りの、ちょっとしたコツをご紹介します。
お弁当作りのポイントと注意点
お弁当作りの基本ルール
お弁当作りを始める前には、必ずしっかり手を洗う、清潔な容器を使うことが基本です。調理器具、菜箸、カップ、ピックも清潔なものを使いましょう。

調理や盛り付けのポイント
◆しっかり加熱 材料の中までしっかり火を通します。作り置きのおかずも必ず加熱しましょう。
◆汁気は少な目に 水分が多いと味が混ざり美味しさが半減するだけでなく、細菌繁殖の原因となります。水分を飛ばす炒り煮、ゴマやかつお節をまぶし、水分を吸わせると良いでしょう。
◆少し濃い目の味付け 糖分、塩分、酸味を少し濃い目に。カレー粉、コショウ、生姜など香辛料を使うと防腐効果があります。
◆しっかり冷まして詰める おかずだけでなく、ご飯やおにぎりもしっかり冷まします。冷ます時間も考えて調理をスタートしましょう。お弁当は彩り鮮やかで華やかに
お弁当は彩り鮮やかに
彩りを鮮やかにすれば、見た目がきれいなだけでなく食欲もわき、バランス良く栄養を摂ることができます。
■赤色 梅干とプチトマトが定番ですが、ニンジンのきんぴらや赤キャベツのマリネも色鮮やかです。
■黄色 玉子焼きが黄色の代表格。玉子焼きに鮭フレークやワカメを入れれば彩りの変化も楽しめます。

カボチャやサツマイモをレモンやオレンジジュースで煮ればサッパリした味になります。
■緑色 ブロッコリーは茹でるだけでなく、カレーパウダーと炒めればスパイシーな一品となります。青じそは水分を取り、仕切りに使えば見た目も鮮やかで傷み防止になります。
■色とりどりのカップやピック おかずを入れるカップや果物に刺すピックも華やかさを演出してくれます。Vol.90 果物を上手に摂り入れ、健康生活を!
2024年1月みかんにリンゴ、冬の果物が手軽に食べられる季節となりました。果物の栄養効果を知り、生活習慣病予防・改善方法をご紹介します。
「果物を食べると太る」の誤解

果糖の摂りすぎはよくない?
果物を食べると太りやすい、血糖値が急激に上昇すると思われがちです。近年の研究では血糖値が緩やかに上昇すると報告されています。食べる時間や量を考えて、おいしい果物で生活習慣病の予防と改善に役立てましょう。
果物に含まれる栄養素
【食物繊維】水溶性・不水溶性どちらの食物繊維も含まれており、腸内の老廃物を排出してくれます。
【塩分排出】カリウムの効果で塩分を体外に排出するため、高血圧予防やむくみの改善が期待できます。
【抗酸化作用】ビタミンCで身体を活性化させます。熱に弱いビタミンCを生で摂取できるのが果物です。
【疲労回復】クエン酸など有機酸が疲労回復やストレスの軽減につながります。果物で生活習慣病予防を
1日200gを目標に
1日の摂取目安は200g、その量としては・・・
【リンゴ 1/2個から1個】幅広い栄養効果が得られます。特に皮には多く栄養素が含まれるため皮ごといただきましょう。
【ミカン 2個】疲労回復や風邪予防。動脈硬化や高血圧の予防にも効果があるとされています。

【バナナ 1本】栄養補給に最適なバナナ。そのため高カロリーと思われがちですが、ご飯や食パンよりも低カロリーなのです。
【イチゴ 約10粒】ビタミンCの宝庫、10粒で1日のビタミンCが補給できます。果物を食べる時間帯
夕食後はエネルギー消費が少なくなるため、身体に脂肪として蓄積されてしまいます。なるべく朝食時に食べることをおすすめします。
Vol.89 乾燥の季節、ドライマウスにご注意を!
2023年11月秋から冬へ、口の中が乾燥しトラブルを起こすのがドライマウス。ドライマウスの症状と改善方法をご紹介します。
ドライマウスの症状と原因
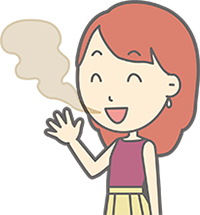
◎ドライマウスの症状
毎年、乾燥する季節になると口の中の唾液が減り、乾燥していると感じることがあれば、ドライマウスかもしれません。主な症状は・・・
・口の中がネバネバする ・口臭が気になる
・口の中や喉、肌が乾燥する ・活舌が悪くなる
・食べ物が飲み込みにくい などです。◎ドライマウスの原因
唾液が減少する原因として・・・
・ストレス ・マスクでの口呼吸
・加齢により口の周りの筋肉が低下や萎縮によるものなどがあります。50歳以上の女性に多く症状がみられます。
3ヶ月以上症状が続く場合は病院での診察を受けましょう。ドライマウスの対策と改善方法
☆生活習慣で改善
軽い症状のドライマウスなら、生活習慣を見直すことで症状を改善することができます。
【よく噛んで食べる】よく噛むことで唾液が分泌される。
【キシリトール入りガムやシュガーレスの飴を噛む】糖分入りのガムや飴は逆に虫歯になってしまうため気をつけましょう。
【あごの下をマッサージ】あごの下、耳の下にある唾液腺を軽くマッサージすれば唾液が分泌されます。
【歯磨きやうがいをする】口の中を清潔にでき、水分を補えます。

【保湿剤やジェルの活用】粘膜を保護し、口全体の潤いを保ちます。☆病気予防対策にも
唾液の量が減ると、虫歯や歯周病などの口の中の病気だけでなく、風邪、インフルエンザ、誤嚥性肺炎などにもかかりやすくなってしまうので気をつけましょう。
Vol.88 疲れた身体にやさしい一杯の味噌汁!
2023年9月夏にたまった疲労が蓄積されるこの時期こそ、味噌汁が効果的。手軽に作れ、身体にもやさしい味噌汁をご紹介します。
味噌汁は優れた栄養食

◎食欲のない時でも一杯の味噌汁を
一年で一番体調を崩しやすいのがこの時期。温度差による自律神経の乱れ、冷たい物の食べ過ぎ飲み過ぎ、睡眠不足など様々な原因があります。
味噌にはタンパク質、ビタミン、ミネラル、脂質、炭水化物の5大栄養素が含まれる優れた食品です。温かい味噌汁で身体の不調を整えましょう。◎簡単手軽に本格的なダシ
ダシの材料を水につけ一晩冷蔵庫に入れておくだけで本格的なダシが取れます。かつお節×昆布、煮干×昆布、干し椎茸×かつお節など好きな材料を組合せます。1リットルの水に対し具材約20gを目安につけ、冷蔵庫に一晩置きます。日持ちは2~3日、使い切らない場合は製氷皿で冷凍し、2週間で使い切りましょう。
ダシの材料は乾燥しているものが多いため、フードプロセッサーやミルサーなどで粉砕し、ダシの素を作ることもできます。たっぷり具材で栄養を効率摂取
☆栄養素を効率的に摂取
【夏野菜】まだ夏野菜が手に入ります。特にトマトはグルタミン酸とかつお節のイノシン酸でうま味アップ。
【きのこ】疲労回復に効果的なビタミンDが多く含まれています。きのこ自体がうま味を出すので数種類のきのこを
組合せ、煮る時間差で歯応えを楽しみましょう。
【薬味】大葉、生姜、ねぎなどは体を温め、血の巡りを良くする効果があります。生姜は薄切り、すりおろし、みじん切りと切り方で味の変化が楽しめます。
☆好きな味噌でお気に入りの味を
【米味噌】最も多い種類があり、地方により甘口、辛口があるため、お気に入りの味を探し、ブレンドすることも楽しんでみましょう。
【麦味噌】九州地方に多く、淡色で甘味が特徴です。
【豆味噌】熟成期間が長いため、色が濃く赤褐色です。うま味とコクで濃厚な味わいが楽しめます。Vol.87 五感で夏を快適に過ごしてみませんか!
2023年7月古くから日本では五感で季節を快適に過ごしてきました。夏に向かう時期を五感で楽しむ生活様式をご紹介します。
伝統の生活様式で涼を感じる

◎涼しさを感じる知恵
梅雨から夏にかけて高温多湿の時期、年々暑さが厳しくなってきています。日本には視覚、聴覚、触覚、味覚、臭覚の五感で涼を得る知恵がたくさんあります。熱中症対策として電化製品を上手に使い、五感を働かせ環境にもやさしい涼を得る生活をおくってみませんか。
◎体感温度を下げるポイント
暑く、ジメジメした時期を快適に過ごすには室温を下げることが大切なのですが、体感温度を下げることで快適に過ごすこともできます。室温が同じでも、無風と風が通るのでは感じる温度が違うため、対角線にある窓を開け、風の通り道を作りましょう。
風通しは服装選びにも大切です。麻は通気、吸湿、速乾などの機能を持つ優れた素材で、襟元や袖口が広いものを着れば、より風通しがよく放熱しやすくなります。五感を取入れ快適に過ごす
☆五感で愉しむ涼
【視る】ブルー、グリーン、水、ガラスなど涼しさを感じるものを室内に取入れてみましょう。ガラスの器に水草を浮かべるだけでも涼しさを演出してくれます。
【聴く】夏の涼しさを感じる音といえば風鈴。澄んだ高音で風の流れをイメージでき、涼感を誘います。川のせせらぎ音をBGMとして流すのも効果的です。

【触れる】直接肌に触れる寝具や衣類は通気性の良い物を選びましょう。い草、籐、竹素材の敷物をリビングに敷くのもひんやり効果が得られます。
【味わう】暑い時期にとれる野菜には身体を冷やす働きがあります。キュウリ、トマト、ナス、ゴーヤなどを積極的に摂りましょう。
【香る】ミント系の匂いが涼しさを感じる代表格です。ハッカ油を数滴コットンなどに含ませ風の通り道や扇風機にあて、爽やかな香りを感じましょう。他にもお風呂に数滴入れれば湯上りに爽快感が得られます。Vol.86 睡眠の質をアップさせて体重管理を!
2023年5月ぽかぽか陽気で、ついウトウトが気持ちの良い季節となりました。睡眠の質を上げ、体重増加を防ぐ方法をご紹介します。
睡眠不足と体重増加の関係

◎睡眠不足で起きる体重増加
睡眠不足になると自律神経のバランスが崩れ、寝ている間に分泌されるホルモン量も減少します。そのため、食欲を抑制させるレプチンの分泌量が減り、食欲を増進させるグレリンの分泌が増えて、体重増加につながるのです。
また、睡眠不足のため、日中の活動量が低下し運動不足となり、体重が増加することもあります。◎寝すぎは逆効果
内臓脂肪が溜まりにくい睡眠時間は6~7時間といわれ、脂肪を分解する成長ホルモンの分泌を促してくれます。午後10時~午前3時が成長ホルモンの分泌が活発となる時間帯です。この時間にしっかり睡眠を取るように心掛けましょう。
逆効果となるのが長時間の睡眠です。長く寝ることで日中の活動量が低下し、基礎代謝が落ちてしまいます。また、食事の時間が不規則になり睡眠の妨げとなります。体重管理のためのポイント
☆ぐっすり眠るための食事
【朝食】睡眠の質を上げるために、朝食から豆製品、乳製品、バナナなどを積極的に摂るようにしましょう。ヨーグルトにバナナやきな粉を入れていただきます。
【おやつ】晩ごはんを食べすぎないためには、おやつも効果的。コーヒーや紅茶のおともにGABA入りチョコレートがおす
すめです。GABAにはストレスを軽減させる効果があるとされています。
【夕食】睡眠時間の3時間前には済ませましょう。脂肪や油の多い食事は消化に時間がかかるため気をつけましょう。ゆっくり、よく噛んで食べれば満腹感も得られ就寝までの間食を防いでくれます。また、寝る前のアルコールは眠りが浅くなり、睡眠の質を落としてしまいます。
☆寝る前のスマホ厳禁
寝る前にパソコンやスマホを見ると画面の光の刺激により眠りが浅くなってしまいます。
Vol.85 毎日の献立づくりで脳の活性化術!
2023年3月少しずつ春めいて、買物に出かけるのも苦にならない季節となりました。毎日の献立づくりで脳に刺激を与え、活性させる方法をご紹介します。
料理づくりで活性化する脳
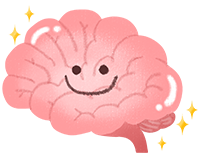
◎料理で脳のトレーニング
毎日の家事の中で献立を考えるのは一苦労です。料理を作るにはメニューに偏りがないか、材料の買物、調理法、調理の段取り、盛り付けなど頭を働かせることで脳に刺激を与えます。
天気の良い日は運動がてら、少し足を伸ばし、普段行きつけないスーパーで新しい発見をするのも脳に元気を与えてくれます。◎手指を使って感覚を刺激する
料理を作る際、包丁で材料を切るだけでなく、指で野菜をちぎる、材料に味をしみ込ませるためにもみ込む、粉をこねるなど手指を使って繊細な作業を行っています。その指先からの感覚が脳への刺激をアップさせてくれます。
自分で調理すれば、身体の健康を考え塩分控えめ、香辛料を使って味を変化させるなど、脳と身体のどちらにも効果が期待されます。脳の働きを活性化させる食べ物
☆脳にいい食べ物
【青魚】脳を活性化する脂肪酸のEPAとDHAが多く含まれています。手軽に使えるサバ缶やオイルサーディンは汁ごと使い切りましょう。
【大豆食品】記憶力や思考力を高めるレシチンが含まれています。野菜や果物に含まれるビタミンCと食べると吸収が良くなります。
【緑黄色野菜】ブロッコリー、カボチャ、ニンジンなどに多く含まれるビタミンやカロテン。電子レンジで簡単に調理ができるので、積極的に摂り入れましょう。
【チョコレート】カカオの含有量が80%以上のダークチョコレートが脳の血流を良くする効果があります。
☆よく噛んで食べる
よく噛んで食べると脳に刺激を与え、記憶力がアップするといわれています。また、よく噛むことで食べ過ぎを抑制し、肥満予防となります。
Vol.84 冬のお悩み、かかとの角質・ひび割れケア!
2023年1月冬になると毎年悩まされる足の乾燥、かかとのガサガサやひび割れ。ちょっとしたケアで改善される、冬のお悩み対処方法をご紹介します。
冬の足の乾燥・かかとのひび割れ
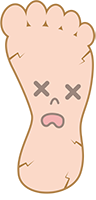
◎乾燥からくる足の症状
冬は暖房や熱めのお風呂に入るなど、乾燥からくる肌トラブルが多い季節です。
脱いだ靴下やタイツにつく粉ふきやお風呂上りに起きる太ももやスネのかゆみ。寒さ対策のために履く、タイツや厚めの靴下は化学繊維製品が多く、速乾性が高いため、肌の水分も奪ってしまいます。脱ぎ着するたびの摩擦でさえも肌には刺激となります。◎かかとの厚みからくるひび割れ
足の裏の皮膚は体重を支えるため、もともと厚いのですが、立ったり歩いたりする衝撃や摩擦でますます厚くなっていきます。かかとには皮脂腺がないため、この角質層といわれる皮膚が厚くなると、水分不足を起こしてしまい、ひび割れが起こります。
厚くなったかかとのひび割れが出血したり、ひび割れの傷みをかばったりするため、足腰に負担を掛ける歩き方をしてしまうこともあります。気をつけましょう。足の乾燥トラブル対処法
☆日常生活での対処法
【暖房器具】 暖房器具を使用する際は、加湿することを心掛けましょう。
【入浴】 肌に保たれている成分を保つためには、40℃以下の温度で。体を洗う時はゴシゴシこすらず、石鹸を泡立てて手で洗うだけでも汚れは落ちます。
保湿効果のある入浴剤を入れたり、入浴後すぐにクリームで保湿したりと、できるだけ乾燥時間を防ぎます。
☆角質ケアでひび割れを防ぐ
【角質を取り除く】 やすりや軽石で角質を落とす場合は皮膚を傷付けないよう注意しましょう。刺激を与えることで逆に角質が厚くなることもあります。
【保湿】保湿効果の高いクリームを入浴直後、就寝前、外出時靴下やストッキングを履く前に塗ると乾燥を防いでくれます。
【正しいサイズの靴】靴の中で足が動かない、程よいクッション性のあるものを選びましょう。Vol.83 この時期おすすめ、カーテン洗濯術!
2022年11月カーテンの汚れは、嫌なニオイやカビ,ダニの発生原因となります。冬が来る前のこの時期にすっきり、カーテンの洗濯術をご紹介します。
忘れがちなカーテンのお手入れ
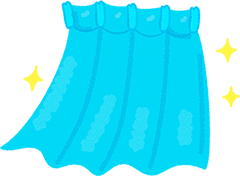
◎カーテンの洗濯頻度は
お部屋の掃除はこまめにしていても、忘れてしまいがちなカーテンのお手入れ。砂ぼこりや花粉、台所の油汚れや調理中の煙も付着し、部屋のニオイの一因となることがあります。これからの季節は窓の結露によるカビやダニの発生源にも。
紫外線やカビで繊維が劣化するのを避け、カーテンを長持ちさせるためにも、半年に一度の洗濯をおすすめします。窓に近いレースのカーテンは汚れも多いのでこまめに洗濯しましょう。カーテンよりは薄地のため乾きも早く、こまめに洗濯することで、カビも発生しにくくなります。◎必ず洗濯表示を確認
カーテンについている洗濯表示で洗濯機可、手洗い可を必ず確認します。他にも洗濯水流や温度表示にも注意してください。素材により使う洗剤も違うため、使用する洗剤の確認も忘れずに。
効果的なカーテンの洗濯方法
☆洗濯する前のひと手間
【ホコリを落とす】はたきや掃除機でおおまかにホコリを落としましょう。その際は生地を傷めないよう優しく扱います。
【カビの有無】カビが発生していたら、酵素系漂白剤とぬるま湯でつけおき洗いしましょう。この際も漂白剤を使用しても大丈夫か洗濯表示を確認してください。
☆からりとした晴天の日に
【カーテンフックは必ず外す】面倒でも必ずフックは外します。生地の破損原因となってしまいます。
【ドレープに従ってジャバラ状にたたむ】縦横それぞれをジャバラ状にたたみ、洗濯ネットに入れます。
【洗濯表示にある洗剤で】表示がない場合は中性洗剤で洗います。
【洗い終わったらすぐに干す】シワ予防のためにも脱水が終わったらすぐにフックを取付けカーテンレールに吊るします。Vol.82 失敗しないローリングストック方法!
2022年9月地震や台風などに備え、食品を備蓄し、食べた分だけを補充するローリングストック。無理なく続ける方法をご紹介します。
ローリングストックとは?

◎ローリングストックってなに?
災害用の非常食を備蓄するのではなく、日常的に食べている食品を少し多めに買い揃え、食べた分だけ、また新しいものを補充することで備蓄ができることをローリングストックといいます。
缶詰、レトルト食品、フリーズドライ食品など、普段から食べている食品がもしもの時の非常食となります。◎食品だけでなく日用品も
日頃から防災グッズを用意している方も多いと思います。防災グッズ以外にも備蓄しておきたい日用品があります。
【必需品】トイレットペーパー、ウエットティッシュ、除菌クリーナー、乾電池、カセットボンベなど
【キッチン用品】ラップ、調理用ナイロン袋、ジッパー付き袋、大型ビニール袋など
【衛生用品】常備薬、使い捨てマスク、救急ばんそうこう、生理用品などローリングストックを続けるコツ
☆自分の好きな食べ物を
気付いたら賞味期限切れや、食べきれなかったなどがローリングストックを続けられない原因です。
うまく続けられるコツとして、普段から好んで食べているものを選びましょう。自分の好きなものなら賞味期限切れになりにくいでしょう。
☆管理のしやすい保存方法
【種類ごとに分ける】レトルト食品、乾麺、缶詰と種類ごとケースに立てて保存すると一目で何があるかがわかります。
【重いものは下に収納】お米や水など重いものはなるべく床に近い場所に保管しましょう。災害時の落下防止にもなります。
【賞味期限順に】備蓄の基本として賞味期限が近いものを必ず前が原則です。補充する時は必ず後ろに入れましょう。Vol.81 夏こそ火を使わない簡単クッキング!
2022年7月暑い夏の食事づくりは一苦労。電子レンジや炊飯器など調理器具を使い、火を使わず簡単にできる食事づくりをご紹介します。
電子レンジだけじゃない調理器具

◎火を使わない調理器具
夏の台所は暑さとの戦いです。なるべく火を使わず便利な調理器具を使い食事を作ってみませんか。
【電子レンジ】
お皿にラップを掛ける調理だけでなく、電子レンジ用調理器具も活用してみましょう。蒸し料理ができるシリコンスチーマー、肉や魚に焼き目がつくプレートなどもあります。電子レンジにはターンテーブルタイプとフラットタイプがあります。ターンテーブルは中央より外側に食材を置き、フラットタイプは中央に食材を置くとむらなく温まります。
【電気炊飯器】
炊飯器を使って調理する場合は調理、煮込メニューがあるものを使用しましょう。必ず最高量を守り、吹きこぼれやすい材料には注意が必要です。
【ホットプレート】
ホットプレートは家族で囲んで食事ができる便利な調理器具です。焼肉やお好み焼以外にも蓋を使えば蒸し料理も簡単にできます。火を使わず時短で簡単レシピ
☆調理家電をフル活用
【下ごしらえ】
ラップをピッタリかけると温め直しのしっかり加熱、フワッとかければかぼちゃやジャガイモの下処理などの長時間加熱に適しています。
【揚げないコロッケ】
柔らかくしたジャガイモやカボチャに電子レンジで加熱したひき肉やタマネギ、ニンジンを混ぜて、油を吸わせて加熱したパン粉を上に掛ければサクサク食感のコロッケの完成です。
【炊飯器で作る夏野菜オムレツ】

アスパラガス、タマネギ、パプリカ、ベーコンを食べやすい大きさに切り分けます。卵を溶き粉チーズ、塩、コショウに野菜を混ぜ合わせオリーブオイルを塗った炊飯器で加熱します。
【ホットプレートで作る夏野菜カレー】
ホットプレートに今が旬の夏野菜や鶏肉を入れ炒め合わせます。夏野菜から出た水分でカレールーを溶かし、ミニトマトや串切りにしたトマトを添えると鮮やかな彩りだけではなくコクが出ておいしく仕上がります。Vol.80 オーラルケアでお口の健康を保ちましょう!
2022年5月在宅時間が長くなり、つい食べ物やお菓子などを食べてしまいます。食後のお口ケアで健康を保つ方法をご紹介します。
お口の健康を保つオーラルケア
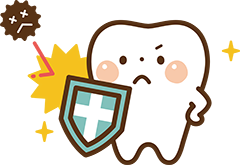
◎オーラルケアとは
オーラルケアとは歯だけではなく口内全体の清潔、健康を保つことです。
口内の汚れから引き起こされる病気もあり、身体全体の健康を維持するためにも、口内を清潔に保つオーラルケアが大切です。◎虫歯や歯周病以外の病気も
【虫歯・歯周病】歯についた汚れや食べかすが残ったままでは虫歯になってしまいます。歯周病は歯と歯ぐきの間に繁殖する細菌に感染し、歯の周りに炎症が起こる病気です。進行すると歯を失ってしまうこともあります。
【誤嚥性肺炎】口内が汚れていると、細菌が繁殖しやすくなり、その細菌が肺に入ってしまうと引き起される病気です。
【口臭】口内に食べかすが残っていると歯周病菌のガスや、舌に細菌が繁殖する舌苔が増えてしまい口臭の原因となります。オーラルケアの種類とやり方
☆商品の種類と選び方
【デンタルフロス】デンタルフロスは細い繊維の束で、歯と歯の間に入れ、歯面に沿わせて上下に動かし汚れを取り除きます。
【歯間ブラシ】歯と歯の隙間に合ったサイズを選びましょう。大きいサイズを無理やり歯間に挿入すると歯肉を傷つけてしまいます。
【舌ブラシ】舌の上が白くなる舌苔を取り除くには舌ブラシを使います。舌を傷つけると逆効果のため力を入れず、1日1回までとします。
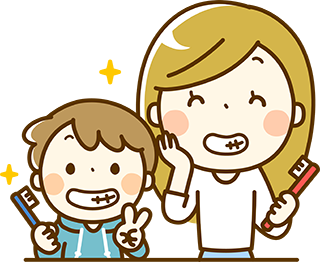
【デンタルリンス】液状のため口内全体に薬剤が浸透します。就寝前に行うのが効果的です。☆歯医者さんで定期的な検診を
セルフオーラルケアも大切ですが、プロケアと呼ばれる定期健診も重要です。早期の虫歯発見や歯周病の原因となる歯石を取り除くことは、やはり定期健診で行ってもらいましょう。
最近の生活通信
- Vol.94 季節の変わり目に起こる体調不良に要注意!
- Vol.93 上手な夏野菜の選び方と保存方法!
- Vol.92 調味料だけじゃない、日常生活での塩活用法!
- Vol.91 ランチに行楽においしいお弁当作りのコツ!
- Vol.90 果物を上手に摂り入れ、健康生活を!
過去の生活通信
© 株式会社山野. All Rights Reserved.

