山野の生活通信
皆様の健やかな毎日にお役に立てるよう、季節にあわせた情報をピックアップしてみました。
Vol.33 お酢を取り入れた夏の食生活!
2014年7月さっぱりした食事が恋しい季節です。お酢を上手に取り入れた食生活で健康的にこの夏を乗り切りましょう。
お料理の名脇役
◎下ごしらえや保存性向上に
<素材の色をきれいに>
ごぼう、れんこんなどアクの強い野菜やカリフラワーは酢を加えてゆでると、白くきれいにゆであがります。
<防腐作用>
お酢の防腐作用で料理を長持ちさせることができます。例えばお寿司。魚が腐らないように考え出された調理法だと言われています。ピクルスもお酢を使った野菜の保存食です。◎調理をサポート

<煮魚をおいしく>
お酢は短い時間煮るとたんぱく質を固める働きがあり、魚の煮くずれが防げます。また、生臭さが和らぐ効果も。
<お肉を柔らかく>
お酢は長時間煮こむとカルシウムやたんぱく質を分解し、お肉料理が柔らかく仕上がります。お酢の種類と特徴
☆穀物酢
米や麦、とうもろこしなどの穀物を原料にした一般的なお酢。価格が安いので加熱調理用のお酢としてだけなく、台所まわりの除菌用としても手軽に使えます。

☆米酢と黒酢
米だけを原料に使った純米酢、玄米だけを使った玄米酢、米酢をねかせて熟成させた黒酢があります。
米酢はお寿司や酢の物など日本料理に最適。黒酢は長期間熟成させ発酵したことで、アミノ酸などの栄養が豊富で独特の色がついています。☆バルサミコ酢
イタリア料理には欠かせないバルサミコ酢は、甘みの強いぶどうを樽に詰め、数年かけて発酵・熟成させたお酢。西洋料理の仕上げに数滴たらすだけで深い味わいが得られます。
Vol.32 知っておきたい傘のマナー!
2014年5月傘をさす機会の増える梅雨。傘の扱い方にも人柄が表れます。さりげない心遣いで雨の日のマナー、身につけましょう。
傘の開き方、閉じ方
◎開くとき

傘を開くとき、バサッと開いていませんか?
上に向けて開くと、骨の先端が顔の高さにくるので周りの人にひっかける場合があります。ワンタッチ傘は勢いよく開くものが多いので、要注意。傘先を斜め下に向け、周囲を確認してから開きましょう。◎閉じるとき
閉じるときも同じように、人がいる方向に向けて傘を傾けないようにしましょう。傘をさしたまま少しすぼめてから下に向け完全に閉じてください。
水滴を落とすときもクルクルッと回したりバサバサ開閉したりすると、周りに水滴が飛び散ってしまいます。閉じた傘先を下に向けて軽く数回振るようにしましょう。傘のさし方、持ち歩き方
☆傘をさして歩くとき
傘を肩にかけ、斜めにさして歩いている姿をよく見かけます。しずくで服がぬれるだけでなく、後ろの人の視界もさえぎってしまいます。傘は体の中心でまっすぐ持ちましょう。
☆傘を持ち歩くとき
腕に掛けた傘先が飛び出して周りの人に当たることもあります。閉じた傘を持ち歩くときは、傘先が周りの人に当たらないよう、傘先をまっすぐ下に向け、なるべく自分の体に引き寄せて持つよう心がけることが大事です。
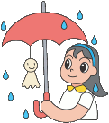
☆電車に乗るとき
ぬれた傘で周りに迷惑をかけないよう、軽く水滴を落とし、傘をたたんでベルトを閉めてから乗車します。乗車後は体の正面で立てて持ちます。
Vol.31 おいしい春野菜で健康ライフ!
2014年3月日ごとに暖かくなり、春のきざしが感じられる今日この頃。旬の野菜をたっぷり食べて、ヘルシーライフのスタートです。
苦味もおいしい山菜
◎アクも栄養のうち

春を告げる野性の植物のうち、食べられるものが山菜です。ほろ苦さが特徴で、これはアルカロイドという成分が新陳代謝を活発にする働きがあるとか。アクを抜き過ぎないのが、山菜をいただくときのポイントです。
◎アク抜きアレコレ
わらび、ぜんまい、ふきのとうなどは、しっかりアク抜きをしましょう。熱湯に塩と重曹を入れてゆで、沸騰したら水にさらして一晩置きます。
たらの芽、うどなどはゆでた後、水に少しさらします。アクが気にならなければそのままでもOK。
ふきは塩で板ずりをした後、たっぷりの水でゆで、水にさらします。毎日食べたい春野菜
☆春キャベツ
1年中出回るキャベツですが、早春から初夏にかけて店頭に並ぶのが春キャベツ。巻きがゆるくて葉が柔らかく、甘みがあります。生食に向いており、サラダにおすすめです。
☆新タマネギ
通常、タマネギは収穫してから1ヶ月くらい風にあて乾燥させて出荷されますが、新たまねぎは乾燥させずに出荷したもの。皮が薄くて柔らかいのが特徴。みずみずしく辛味が少ないので、生食でおいしくいただけます。
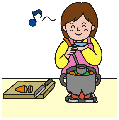
☆さやえんどう
鮮やかな緑色のさやえんどうは、えんどう豆を早採りしたもの。ビタミンCやカロテンも豊富に含まれています。長く空気に触れると、しおれてしまうので、調理はお早めに。
Vol.30 今年の冬もエコ暖房!
2014年1月1年で最も寒い季節がやってきました。暖房器具を上手く使いこなし、日頃の工夫で冬の節電に心がけましょう。
暖房器具をうまく使う

◎特徴を理解して使い分け
冬は石油ストーブで省エネを考えている方、広い部屋を暖めるなら石油ストーブは効率がよくありません。器具ごとの特徴を理解しましょう。
・エアコン:部屋全体を暖めて温度を保つ
・電気ストーブ:足元を直接暖めるなど局所暖房
・石油、ガスストーブ:部屋を一気に暖める
寒い部屋を石油ストーブで一気に暖め、暖まった後はエアコンで温度調節を行なうと効率的です。◎温度設定が重要
エアコン(6畳に対応する機種)の設定温度を21度から20度に下げれば、1日9時間6ヶ月使用で電気代が約1,200円節約できます。
また、設定温度20度で運転時間を1時間短くすると、6ヶ月で約900円電気代の節約に。体感温度を上げる工夫
☆着るものを増やす
暖房器具だけに頼らず、着るものにも工夫しましょう。
カーディガンを1枚はおれば2.2度、ひざ掛けで2.5度、ソックスで0.6度体感温度が上がるといわれています。☆首と足先を温める
冷えやすい首と足先を温めるとより効果的です。
脳に血液を送る頚動脈が首の体表近くを通っているため、首が冷えると頚動脈を流れる血液が冷えてより寒く感じるのです。
足先は心臓から遠く血流も弱いため、冷えを感じやすいのです。 ☆湿度を上げる
☆湿度を上げる同じ室温でも湿度が高ければ体感温度はアップ。湿度が20%から60%に上がれば、体感温度は約2度上がります。
Vol.29 冬は高血圧に警戒!
2013年11月冬は寒さで交感神経が緊張し、血管が収縮し血圧が高くなる時期です。この時期に気をつけたい高血圧対策をおさえましょう。
高血圧について

◎そもそも血圧って?!
血圧とは血液が血管の壁にあたえる圧力のこと。心臓が収縮して血液を送り出した瞬間は、血管に最も強く圧力がかかる収縮期血圧(上の血圧)、心臓が拡張して血圧が最も低くなったときは拡張性血圧(下の血圧)と呼ばれます。
高い圧力が長い間血管にかかると、血管の壁が厚くなって血管が硬くなり、血管の一部が狭くなる動脈硬化になり、心臓にも負担がかかります。◎高血圧の種類
日本高血圧学会による高血圧の基準は、収縮期血圧140mmHg、または拡張期血圧90mmHg以上。
高血圧には原因が特定できない本態性高血圧と別の病気が原因で起こる二次性高血圧の二種類があります。9割が前者のタイプで、加齢に伴って増加します。高血圧対策アレコレ
☆塩分控えめの食生活
最も重要なのは、塩分を控えること。血圧が高い人は、1日の塩分摂取6g未満が目標です。塩分の排出を促すカリウムが豊富な野菜や果物も積極的に取りましょう。
☆有酸素運動
ウォーキングのような有酸素運動を1日30分目安に行ないましょう。運動中は血行が良くなり一時的に血圧が上がりますが、継続し運動を行なうと血圧が下がってきます。
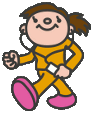 ☆温度差を少なく
☆温度差を少なく季節による血圧変動は冬が一番高くなります。廊下やトイレ、浴室も十分に暖かくし、部屋ごとの温度差を少なくしましょう。
お風呂は熱いお湯を避けて長湯をしないこと。38~42℃くらいのお湯に5~10分程度で。Vol.28 秋こそハウスダスト対策!
2013年9月ダニ繁殖シーズンの夏を終え、死骸が大量に発生する秋。ハウスダストの被害が出る前にすぐにできる対策を始めましょう。
ハウスダストあれこれ

◎ハウスダストって?!
「ハウスダスト」とは文字どおり、家の中にあるホコリ。ダニのフンや死骸、フケや花粉、カビの胞子のような小さなものまで様々です。
ダニのフンや死骸は乾燥すると細かく砕け、空気の動きで舞い上がり、のどの奥まで吸い込んでしまうこともあります。
アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎や気管支喘息などの原因になる困りものです。◎ハウスダストを防ぐには
ダニは高温多湿を好みます。温度と湿度を管理して、ダニの発生を抑えることが肝心です。
湿度が高くなりがちなところは時々、風を通して乾燥させたり除湿剤など活用したりして予防します。やはり一番大切なのは、こまめに掃除を行なうことです。お手入れのポイント
☆カーペット
カーペットの毛の奥に詰まったハウスダストは、一方向に掃除機をかけただけでは取りきれません。タテヨコ十字に1㎡あたり20秒を目安にゆっくりかけましょう。
☆ふとん
ふとんは寝ている間にかく汗で湿っています。まず、よく干して湿気を飛ばしましょう。
取り込む時にふとんをたたくと、ハウスダストが細かく砕けて取れにくくなるので軽く手で払う程度に。取り込んだ後に掃除機をかければ効果的です。☆フローリング
 いきなり掃除機をかけると排気でハウスダストが舞い上がってしまいます。 。
いきなり掃除機をかけると排気でハウスダストが舞い上がってしまいます。 。
掃除機をかける前に拭き掃除を行い、ハウスダストを取り除いておきましょう。Vol.27 夏こそ電子レンジクッキング!
2013年7月「夏の台所は暑くて」という方。電子レンジなら熱気とは無縁です。便利なシリコンスチーマーの使い方もご紹介します。
電子レンジの特徴を活かす

◎電子レンジの仕組み
電子レンジの中にあるマグネトロンという装置で作られるマイクロ波という電波が食べ物を温めます。
金属食器は電波が反射して火花が散るなど故障の原因になるので、電子レンジには使用しないようにしましょう。卵のように密閉されているものは爆発の危険があります。◎下ごしらえに活用しましょう
野菜をゆでるなどの下ごしらえを電子レンジで行なうと、時間が短縮できるだけでなく、ビタミンCなどの損失も少なくてすみます。
また、かぼちゃやブロッコリーなど電子レンジで加熱してから油で調理すれば、調理時間と油の吸収量が短縮されます。暑い日にはぜひ活用したいですね。シリコンスチーマー活用法
☆シリコンスチーマーって?!
シリコンスチーマーとは、素材に高密度シリコンを使ったキッチン用品です。
電子レンジの中でうまくマイクロ波が届くよう作られており均一に加熱され、フタがぴったりおさまるのでふきこぼれの心配がありません。食べ物から出るうまみを蒸気で逃がすことなく、ふっくら、しっとり仕上がります。☆調理のコツ
手軽にできる野菜の蒸し物なら野菜を洗った水分でも大丈夫ですが、水分が少ない食材は大さじ1杯程度の水を入れて加熱します
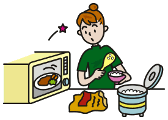 。
。
加熱時間は短めにして、様子を確認しながら加熱します。加熱しすぎると、食材が硬くなったり焦げたりしてしまうこともあります。途中で取り出して混ぜれば加熱ムラも防げます。Vol.26 部屋干しを快適に!
2013年5月梅雨の部屋干しの洗濯物、なかなか乾かずニオイも気になります。洗濯物の洗い方や干し方を工夫し、「部屋干し上手」を目指しましょう。
洗う時のポイント
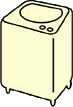
◎洗濯物の雑菌を減らす
洗濯物を濡れたものと一緒に洗濯槽に入れてフタをしていると、雑菌が増えてニオイのもとに。
汚れものは通気性のよいカゴなどに入れ、湿ったものはある程度乾かしてから洗いましょう。◎洗濯物は詰め込み過ぎない
洗濯物を詰め込みすぎると汚れ落ちが悪くなり、残った汚れが酸化分解する過程でニオイが発生します。
洗濯物は表示されている分量の7~8割を目安にしてください。洗剤時は除菌効果のある酸素系漂白剤をプラス。
すすぎに柔軟剤を加えると乾きやすくなるのでおすすめです。室内干しをさわやかに
☆空気に触れる面積を多く
洗濯物を速く乾かせば、それだけニオイを押さえられます。洗濯物に風が通りやすくなるように、生地が重ならない干し方を工夫しましょう。
ズボンやスカートは裏返して筒状に、乾きにくいタオルやシーツは蛇腹に干します。☆洗濯物は部屋の中央で干す
洗濯物は空気が循環する部屋の中央で干しましょう。窓を閉め切った部屋でも部屋の中央なら空気が動きます。
逆に、窓際は空気が流れにくいだけでなく、カーテンのホコリで洗濯物が汚れる場合もあります。 ☆部屋の湿気を取る
☆部屋の湿気を取る部屋の湿度が高いと洗濯物も乾きにくいため、雑菌やカビが生えやすくなります。
エアコンの除湿機能や扇風機で部屋の空気を循環させると効果的です。Vol.25 春のホコリ対策!
2013年3月風の強い日が多い春は、お部屋がホコリっぽくなりがちです。住まいからホコリを追い出し、健康でクリーンな暮らしを送りましょう。
意外なホコリの正体

◎ホコリの中身は?
ホコリは室内の空気中に浮遊している様々なチリで、ハウスダストと呼ばれるもの。目に見えるものは、綿ボコリや抜け毛、食べ物のカス、砂や土など。
さらに、目に見えない花粉、ダニ、カビの胞子、微生物などもあります。ホコリに含まれている物質のせいで、アレルギー反応を引き起こすこともあるのでやっかいです。◎ホコリはどこからやってくる?
綿ボコリのように日常生活で発生するものや、土など外から持ち込まれるものがあります。
一旦積もったホコリは、人が動くたびに空気がかき回されて舞い上がってしまうのです。ホコリ撃退作戦
☆ホコリを入れない
ホコリ対策の第一は、ホコリを住まいに入れないこと。目に見えなくても服にはホコリがたくさんついています。
外出先から帰ったら、玄関先で上着を脱ぎ、しっかりはたいてから部屋に入るよう習慣づけましょう。☆換気でホコリを追い出す
現在の家屋は機密性が高く空気の出入りが少ないので、意識的に換気を心がけましょう。風の通り道を長くするために、
なるべく離れたところに空気の入口と出口を作ること。1時間に1回、5分程度こまめに換気を行ないます。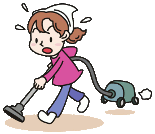 ☆ホコリがたまってしまったら
☆ホコリがたまってしまったら下に積もったホコリはこまめに掃除するしかありません。
特にじゅうたんはホコリがたまりやすいので、こまめに掃除機をかけましょう。黒布でじゅうたんを覆って日光にあてて干すと、ダニ対策に効果的です。干した後は表面を掃除機で吸引してください。Vol.24 土鍋クッキングに挑戦!
2013年1月鍋物で活躍する土鍋ですが、いろんな料理に使えることご存知ですか。土鍋の特徴を知って毎日の料理に役立てましょう。
土鍋の特長と活用法

◎保温力の高さを生かして煮物に活躍
火を止めてもしばらくグツグツ煮えるほど保温力が高いので、余熱で調理できます。煮物や煮豆など、弱火でゆっくり火を通した後、火を止めて仕上げましょう。
素材のうまみを引き出し、煮立たせないので煮くずれも防げます。ガス代も節約できるエコクッキングです。◎遠赤外線効果で蒸料理
土鍋から出る遠赤外線効果のため、短い時間で食材にしっかり火が通るので、食感がふっくら仕上がる蒸しものもおすすめです。土鍋の下に白菜などを敷いて、少しだけ水を入れ火にかけます。沸騰したらシューマイなど具を入れて中火で蒸します。
大切に使うための注意点
☆土鍋を買ったらおかゆを炊きましょう
土鍋は陶器なので、細かな穴が開いています。ひび割れや水漏れを防ぐためには穴をふさいでおく必要があります。
新しい土鍋を買ったらおかゆを炊いたり米のとぎ汁を入れたりして弱火でゆっくり煮てください。お米のでんぷん質が穴をふさいでくれます。☆ひび割れに注意
土でできた土鍋は空焚き厳禁です。急激な温度変化に弱いため、鍋底が濡れたまま火にかけたり、熱いうちに水に浸けたりすると、ひび割れの原因になります。
鍋底は釉薬がかかっていないので、ゴシゴシ洗いに注意しましょう。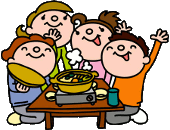 ☆においを取るには
☆においを取るには土鍋の中に料理を入れっぱなしにしておくと、においがついてしまいます。なるべく早く他の容器に移し替えましょう。においを取るには、茶がらをひとつかみ入れて10分くらい煮立てます。
Vol.23 手荒れを防ぐ冬のハンドケア!
2012年11月冬は冷えや空気の乾燥のため、手荒れに悩む人の増える季節。こまめにハンドケアを行えば、手荒れはグンと改善できます。
乾燥を防ぐ手洗い法
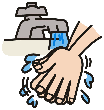
◎刺激の少ない石鹸がおすすめ
殺菌作用の強い薬用石鹸などで何度も手を洗うと、皮膚の脂質が奪われて手が荒れやすくなります。薬用石鹸は外出から帰宅したときだけにして、それ以外は刺激の少ない固形石鹸がおすすめです。
◎洗った後はすぐに拭く
濡れている時間が長いと手荒れしやすくなります。水仕事の多い人は濡れたままで長くいると、気化熱で手の皮膚の表面温度が下がり、しもやけになりやすくなります。洗った後は、すぐに拭くよう心がけましょう。
ハンドクリームで潤いを
☆手洗いの後はすぐにハンドクリーム
手を洗った直後は潤ったようになります。しかし、しばらくすると水分が飛んでいくので、手を洗った後はすぐにハンドクリームを塗りましょう。
洗面所や台所に常備しておくと塗り忘れを予防できます。☆ハンドクリームの種類
ハンドクリームは、親水性のあるグリセリン系と疎水性のワセリン系があります。グリセリン系は内部からの水分を保持し、ワセリン系は皮膚表面から水分が飛ぶのを防ぐ働きを持っています。
皮膚にもともと存在する保湿成分の尿素が配合されている薬用ハンドクリームなら、手荒れを防ぐ効果がさらに期待できます。 ☆ハンドクリームの塗り方
☆ハンドクリームの塗り方ハンドクリームを塗るときは、適量を手の甲に取り、指全体で円を描くように手の甲になじませます。ゴシゴシすり込むと摩擦で肌に負担がかかり逆効果。爪のまわりや、特に乾燥しやすい指の間、関節部分も忘れずに。
Vol.22 秋の夜長の快眠対策!
2012年9月夏の疲れを取るためにもぐっすり眠りたい秋。思うように眠れない方に役立つ快眠対策ご紹介します。
眠りの質が下がる高齢期
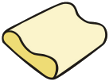
◎年とともに短くなる睡眠時間
年を取ると朝早く目が覚めるといわれるように、年齢とともに睡眠時間は短くなります。また、高齢者になると、寝つきが悪くなる、眠りが浅くなる、途中で目が覚めやすい、朝早く目が覚めるといった不眠症のような症状を訴える人が増える傾向にあります。
◎夜中のトイレは要注意
不眠症の方は夜中に2回以上トイレに行く人が多いようです。トイレまでが遠かったり、明るい光をあびたりすることで、しっかり目が覚めてしまい、再入眠できなくなってしまうことがあります。
ぐっすり眠るための工夫
☆寝る前の環境づくり
スムーズに眠るためには、脳をリラックスさせることが大切です。熱いお風呂に入ったり、頭を酷使するような作業は避けましょう。
部屋の照明は控えめに。どうしても眠れないときは、無理に眠ろうとせず、一度布団から出て気分を変えると自然な眠りに入りやすくなります。☆日常生活の工夫
朝は太陽の光を浴びて体内時計をリセットしましょう。これがないと寝つきが1時間ずつ遅れることになります。
昼寝は昼食後午後3時までに30分程度に。昼寝が長すぎると夜に眠れなくなります。日中は適度な運動を心がけましょう。適度な体の疲れが自然な眠りを誘います。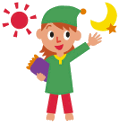 ☆夜中のトイレ対策
☆夜中のトイレ対策夜中のトイレで目が覚めてしまう方は、トイレの近くに寝室を設けてみては。
また、廊下やトイレの明かりは暗めにし、冬など寒い時期は廊下も適度な室温に保ってください。Vol.21 自然派の虫除け対策!
2012年7月夏真っ盛り、蚊やハエなど虫が気になる季節です。化学薬品の防虫剤を使わず、簡単にできる自然派の虫除け対策をご紹介します。
天然のハーブで虫除け
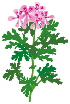
◎蚊の嫌がる蚊連草
ゼラニウムのことで、ヨーロッパでは窓の下にゼラニウムのプランターを置いている家をよく見かけます。特に蚊の嫌がる香りを発するものは、日本では「カレンソウ(蚊連草)と呼ばれます。葉に虫除け効果があり、揺らすと強く香ります。
◎ローズマリーの虫除け効果
樟脳と同じ成分が含まれ、虫除け効果があります。戸外でバーベキューをするときに、茎を周りに散らしておくと、その香りを嫌って虫がよってこないとか。
和風な自然派の虫除け
☆食べ物で虫除け
化学物質過敏症の方にも安心なのが、食べ物による虫除け。
たとえば、キュウリ。蟻はキュウリが苦手なので、蟻が入り込みそうな隙間や蟻の通りそうな場所にキュウリのスライスをおいてみましょう。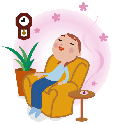 ☆香辛料で虫除け
☆香辛料で虫除け防腐作用などのある香辛料には虫除け効果を期待できるものがあります。乾燥させた唐辛子は米びつに入れておくと虫除けに。ひな人形の保管用にも使用されていたようです。クローブ(丁子)には防虫効果のあるオイゲノールという成分が含まれています。乾燥させて部屋につるしておけばインテリアにも。
Vol.20 食品を長く保存する知識アレコレ!
2012年5月湿気の多いこれからの季節は食品が傷みやすい時期。ほんのひと手間で、食材がグンと長持ちする保存方法をマスターしましょう。
野菜の鮮度を保つには
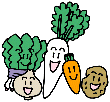
◎野菜が育った状態に適した保存を
野菜が育った状態に合わせて保存するのが長持ちのコツ。 例えば、立って生えている野菜なら、保存する場合も横に寝かせず立てて保存します。 暑いところで育った野菜は極端に冷やし過ぎないようにしましょう。土の中で育った野菜は、土がついたまま保存するほうが長持ちします。
◎葉物野菜の乾燥を防ぐには
ほうれんそうなどの葉物野菜はそのまま冷蔵庫に入れると水分が失われてしまいます。水で湿らせたクッキングペーパーなどで包みビニール袋に入れて保存するとよいでしょう。
冷凍保存のポイント
☆水分の多い野菜は下ごしらえを
食材は冷凍すれば長持ちしますが、生のままで冷凍すると解凍したときに水分が流れ出て食感が変わってしまう野菜もあります。
その場合は、ゆでる、煮る、炒める、すりおろすなど下ごしらえをしておけば、風味や栄養分をあまりそこなわず冷凍保存することができます。☆できるだけ短時間で冷凍する
食品の鮮度や風味を保つにはできるだけ短時間で冷凍する必要があります。そのためには、熱いものはさます、平らにして金属トレイに入れる、小分けにするなどがおすすめ。また、食材の乾燥や霜を防ぐにはできるだけきっちり密封することがポイントです。
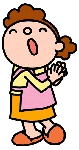
☆上手な解凍のコツ
肉や魚は冷蔵庫内でゆっくり解凍。急ぐときは、水が入らないように流水にさらして解凍します。冷凍保存しても食品の酸化は進んでいくため、できるだけ早く食べましょう。
Vol.19 冬物衣類の上手なお手入れ!
2012年3月いよいよ春到来。セーターなど冬物衣類のお手入れはお済みですか?来年も素敵に装うために、きちんとお手入れしてしまいましょう。
取扱い絵表示を確認しましょう
◎洗濯の前に取り扱い絵表示をチェック
衣類には洗濯の方法を示す取扱い絵表示がついています。型くずれや色落ちなどの失敗がないよう、必ず洗濯前にチェックしましょう。
 液温は40℃を限度とし、中性洗剤を使用、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい。
液温は40℃を限度とし、中性洗剤を使用、洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい。 水洗いはできない。
水洗いはできない。◎洗濯後の干し方も重要
せっかくきれいに洗っても、干し方が間違っていると台なしです。セーターなどは、色あせや黄ばみを防ぐために、直射日光を避け陰干しにしましょう。また、型くずれしないように、平らな場所で干すことをおすすめします。
自分でできるセーターのお手入れ
☆ウールのセーターは水で洗う
洗剤は中性洗剤で。洗濯機で洗うなら、汚れやすい袖口を外側にして折りたたみネットに入れ、手洗いコースで洗います。水温が高いとセーターが縮むおそれがあるので、30度以下の水で。
洗い終わったら、ネットごと両手ではさみ、軽くたたいて全体のシワを伸ばします。形を整えて干せば型くずれの心配もありません。☆アイロンは浮かして
ふんわり仕上げるには、スチームアイロンをセーターから少し浮かした状態でかけます。アイロンを押し付けると繊維が傷むので、1センチくらい浮かすのがコツ。
 ☆しまい方もキッチリ
☆しまい方もキッチリ収納ケースの幅に合わせてセーターをたたんでしまいます。折ったシワがつかないよう注意しましょう。防虫剤を忘れずに、一番上に置いてください。
最近の生活通信
- Vol.93 上手な夏野菜の選び方と保存方法!
- Vol.92 調味料だけじゃない、日常生活での塩活用法!
- Vol.91 ランチに行楽においしいお弁当作りのコツ!
- Vol.90 果物を上手に摂り入れ、健康生活を!
- Vol.89 乾燥の季節、ドライマウスにご注意を!
過去の生活通信
© 株式会社山野. All Rights Reserved.

